節分といえば何をイメージしますか?
「鬼はー外!福はー内!」
と、学校の行事や家族と一緒に豆まきをした
思い出もたくさんあると思います。
そして、恵方巻きの丸かじり。
みんな同じ方向を向いて、
「1本を食べ終わるまで喋ってはいけない」
という風習ですよね〜
元々は関西の風習でしたが、
最近では全国的になってきています。
我が家では、一番偉いおじいちゃんが
一番最初に喋ってしまい・・・
それに他の家族が思わず笑って喋ってしまう、
という毎年のオチがありました(笑)
この節分の「豆まき」と「恵方巻き」以外にもうひとつ、
節分の食べ物があるのをご存知でしょうか?
最近は家で飾られているのを見ないせいか、
意外と知られていないのですが・・・
実は「イワシ」なんです。
その由来や説明をまとめてみました。
子供でもわかる!節分の由来
まず節分の語源ですが、
元々は、
- 立春
- 立夏
- 立秋
- 立冬
の季節を分ける4つの日の前日を指しました。
今は立春の前日だけを指して言われていますが、
これは、冬から春になる時期を一年の境目として、
大晦日のような考えから、今に至っています。
ちなみに節分って、2月3日と思っていませんか?
これ、実は間違い。
毎年、2月2日だったり2月4日だったり、
節分の日程は変わるんです。
ちなみに、2016年は、2月3日。
節分のいわしの飾り方や由来とは?
そして、イワシを飾るようになった由来です。
「季節の変わり目になると鬼が出る」
という昔から怖い言い伝えがあり、
その鬼を退治するためにイワシが用意されたんです。
また、トゲトゲの葉の柊に一緒に刺して
飾って退治するんです。
ちくちく刺さる柊に、鬼が目をついたことがあるから
鬼が苦手なものだとされています。
加えて、焼いたイワシの臭い匂いが大嫌いな鬼は、
そのダブルパンチの攻撃で逃げていく、
と言われているんですね。
鬼が鼻をおさえながら
「おえっ」
とするのを想像したら少しおかしいですね^^
でも、この柊とイワシの鬼退治の歴史は
さかのぼること平安時代から伝わっているのです。
イワシを飾る期間と処分方法
肝心なイワシを飾る場所ですが、
家に入らせないために、玄関や裏口に飾るのが一般的です。
焼いたイワシを、柊の枝に刺して完成です。
私が住んでいるアパートでは、
毎年、大家さんがアパートの入り口に飾っています。
近所の子供が、ちょっと怖がってました^^;
飾る期間ですが、実はこれは地域によっては
1ヶ月近くも飾っておくところもあるので、
全国的に共通ではありません。
ただ、一般的には
節分当日の2月3日〜翌日4日までとされています。
いま住んでいる地域を調べてみると
楽しい発見になるかもしれませんよ。
では、処分方法です。
鬼じゃなくても、私達にとっても
イワシって独特の臭みがある、少しきつーい匂いの魚ですよね。
「外した後は、自分の魔除けでお守りにするのです」
なんて言われたら困ります(笑)
実は、単純な処分方法なので覚えておいてくださいね。
紙に包んで塩を清めて捨てる
というのが一般的な処分方法です。
神社へ持っていったり埋めたりなども可能だそうですが、
塩で清めたら、普通の処分方法で問題ありません。
まとめ
いかがでしょうか。
昔からの風習や文化が、今でも伝わっているのは
本当に不思議で面白いですよね。
特に日本は、世界から見ても
独特な文化がたくさんあります。
一般的にはなっていない文化も、
まだまだたくさんあります。
親日家の外国の方のほうが、
たくさん知っているなんてことも・・・^^;
次の節分にぜひお役立てくださいな。

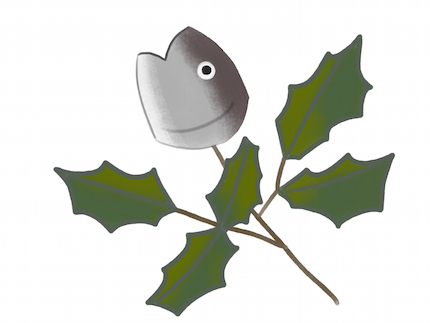



コメント